
在りし日のフチーク
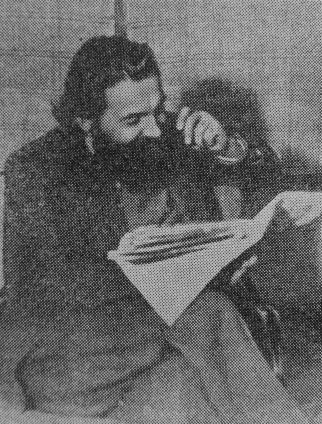
ホラーク博士に扮するフチーク
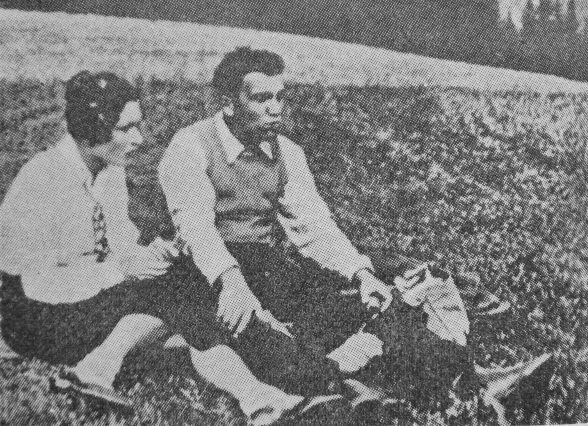
ハイキングを楽しむフチーク夫妻(ユリウス&アウグスチナ)
絞首台からのレポート
ユリウス・フチーク、来栖継、筑摩書房、1968。
序
体をピンと立て、手を膝にしっかり当て、目をペチェク会館の「屋内拘禁所」の部屋の黄色くなった壁に釘付けにしたまま「気をつけ!」の姿勢で腰かけている。これは、確かに瞑想を誘う状況ではない。だが、誰が思想に「気をつけ!」の号令をかける事ができよう。
今となってはもう確かめようもないが、いつ誰が言い出したともなく、このペチェク会館の「屋内拘禁所」に「映画館」という名前がつけられた。天才的な思い付きである。だだっ広い部屋には六つの長いベンチが並び、取り調べ中の人たちが体を固くして腰かけている。彼らの目の前にある裸の壁は映画館のスクリーンさながらである。世界中のあらゆるプロダクションが今まで作った映画をぜんぶ合わせても、新たな取り調べ、拷問、死に呼び出されるのを待つ間に、これらの人々の目がこの壁の上に映写した映画の数には及ぶまい。全生涯の映画、あるいはある瞬間の映画、母の映画、妻や子供の映画、破壊された家庭や台なしにされた生活の映画、勇敢な同志の映画、あるいは裏切りの映画、私があのビラを渡した男の映画、ふたたび流れ出る血の映画、私に戦いの誓いを新たにさせた固い握手の映画、恐怖や勇ましい決意に満ちた映画、憎悪や愛の映画、不安と希望の映画。人生に背を向け、我々のひとり一人はここで、毎日自分の目の前で死んでゆくのだ。しかし、皆が皆、映画のように甦りはしない。
私はここで私の生涯の映画を百回も見た。そのディティールときては千回も見た。今、私はそれを書き記そうとする。よし、書き終える前に絞首吏の縄が私を絞め殺そうとも、あとに残る幾百幾千万の人々がその「ハッピー・エンド」を書いてくれるだろう。
1943春、プラハ、パンクラーツ・ゲシュタポ監獄にて
24時間
1943年4月24日、生暖かい春の夜、時計はもう5分で10時を打つ。
私はびっこの初老の紳士に扮装して、イェリーネク夫妻のアパートを目指した。遅れてはいけない。あの二人の心の美しい人々に、余計な心配はかけたくない。
夫妻、ミレク、それにフリート夫妻も来ていた。
「何を持って来てくれた?」
「チェコ共産党機関紙のメーデー号」
「それは素敵だ」
誰かがベルを鳴らしている。いらだって、ドアをどんどん叩く訪問者。
「開けろ! 警察だ!」
急いで窓へ! 逃げろ! 私はピストルを持っている。援護しよう。しかし、窓の外ではゲシュタポが待機していた。刑事の総数は9人、もし私が発砲すれば、部屋にいる5人の友人が撃たれる。決まった。私は姿を現わす。
私の顔に最初のパンチが見舞われる。ノックアウトするつもりだったのだろう。
「手を上げろ!」
もう一つパンチが見舞われる。さらに、もう一つ。
これは私が想像した通りだった。
模範的なまでにきちんとしたアパートは、いまや横倒しになった家具と壊れた物の山である。
さらに殴打と足蹴。
「歩け!」
彼らは私を自動車に引きずり込む。ピストルが絶えず私に向けられている。自動車の中で尋問が始まる。
「お前は誰だ?」
「ホラーク教授」
「嘘つけ」
彼らは撃たない、その代わりパンチをくれる。
ゲシュタポ本部ペチェク会館。生きてここへ足を入れようとは思わなかった。5階、ここが有名な共産党対策部「2−A1」である。
夜の11時、尋問。ホラーク教授の身分証明書を出すが、偽造と見破られる。
「誰から貰った?」
「警視庁から」
初めてステッキで殴られる。2回、3回、数えてみようか? いや、こんな統計を報告するところはない。
「お前の名は? お前の住所は? 言え! 誰と連絡があった? 言え! 言わないと、殴り殺すぞ!」
ひとりの健康な人間がどれだけの打撃に耐える事ができるか?
背の高い警部が部屋に入ってくる。
「いいか、何もかも分かっているのだ。喋べれ! 手数をかけるな」
手数をかけない事が、裏切る事を意味するとは、妙な辞書もあったものだ。私には、手数をかけないような事はできない。
「縛り上げて、もっ殴れ!」
深夜1時、終電車が車庫へ帰って行く。
「中央委員会のメンバーは誰だ? 印刷所はどこにある? 喋べれ! 喋べれ!」
私は再び殴られる数を落ち着いて数えられるようになっている。噛みしめている唇にしか痛みを感じない。
「靴をぬがせろ!」
なるほど、足はまだばかになっていない。五つ、六つ、七つ、殴られる度に、まるでステッキが脳天まで飛び上がってくるようだ。
2時。プラハは眠っている。どこかで子供が寝言を言っている事だろう。夫が妻の腰に手を回している事だろう。
「喋べれ! 喋べれ!」
私の舌は血の出ている歯茎をまさぐる。そして、どれだけの歯が殴られて抜け落ちたかを数えようとする。数えきれない。12、15、17? いや、それは私を「取り調べて」いる警部たちの数だ。彼らのうちには、もうありありと疲れを見せている者もある。しかし、死はまだ来ない。
3時、早朝は郊外からやってくる。野菜作りの農民たちが市場へくるまで行く。街路掃除夫たちが仕事に出かける。ひょっとすると私はもう一度夜明けを見る事ができるかも知れない。
彼らは私の妻を連れてくる。
「この男を知っているだろう?」
私は彼女に見えないように、口のまわりの血を呑みこむ。しかし、それは馬鹿げている。血は私の唇のいたる所から、そして私の指の先からにじみ出ているのだから。
「この男を知っているだろう?」
「知りません」
彼女は言った。恐怖のそぶりも見せなかった。素晴らしい。彼女は絶対に私を認めない、という誓いを守った。もっとも今となってはそれはほとんど不必要ではあるが。それにしても私の名を彼らに喋べったのは誰だろう?
彼らは彼女を連れ去る。私は精一杯快活な眼差しで、さようならを言った。おそらくそれは快活なものではなかったろう。私には分からない。
4時。夜が明けかかっているのだろうか? カーテンの下りた窓は何の解答も与えない。そして、死はまだやって来ない。私はそれを迎えにいったものか? どのようにして?
私は誰かを殴り返し、床に倒れる。彼らは私を靴で踏み付ける。これがそれだ。すぐ最後がやってくるだろう。髪の黒い警部は私のあごひげを引っ張り、引き抜いたひと握りの毛を満足そうに笑いながら見せる。まったく滑稽だ。私はもう痛みを感じない。
……5時、……6時、……7時、……10時、そして正午。労働者は職場へ行って帰り、子供たちは学校へ行って帰る。商店では物を売っている。家では食事の仕度をしている。たぶん母は、この瞬間に私の事を思っているだろう。そして、同志たちは私が検挙された事を知って、危険防止の手配をしているだろう。もし私が喋べったらどうなる。いや、心配ご無用。私は決して喋べらない。当てにして貰って良い。私の最後はもう遠くはない。これはすべて悪夢だ、恐ろしい熱病の悪夢だ。袋叩き、それから水をぶっかけて蘇らせる。それからまた殴る、そして怒鳴る。
「喋べれ! 喋べれ! 喋べれ!」
しかし、私はまだ死ねない。お母さん、お父さん、どうしてあなたたちは私を、こんな事が耐えられるほど強い体に作って下さったのです?
午後5時、彼らはみんなもう疲れきっている。殴るスピードは落ち、間遠くなり、惰性で続けられているに過ぎない。突然、遠く、計る事のできぬほど遠くから愛撫のように気持ちの良い、落ち着いた静かな声が聞こえる。
「エル・ハト・ショーン・ゲヌーク!(これでもう充分だ)」
それからしばらくあとで、私はテーブルのところに腰をおろしていた。テーブルは落ちて行ってはまた私の所へ帰ってくる。誰か入ってきて私に水をくれた。誰か私に煙草を一本くれたが、それを私は持っている事ができなかった。
階段を降りて、クルマで運ばれる。
背の高いSS隊員(ナチス親衛隊)が、私のそばに立ちはだかり、足で蹴って起き上がらせようとする。蹴っても無駄である。誰かほかの者が私の顔を洗ってくれる。私はテーブルのところに腰をおろしている。どこかの婦人が薬をくれて、どこかいちばん痛むかと聞く。
それから再び何もかも消えてしまう。
我に返ると、監房のドアが私の前に開かれている。太ったSS隊員が私を中へ引きずり込み、ずたずたになったシャツを脱がしてわら布団の上に寝かせる。彼は私の腫れ上がった体に触って、湿布を命じる。
「見たまえ」と彼はもうひとりの男に言って首をふる。「あの連中ときたら何という事をするのだ!」
「朝までもつまい」
もう5分で時計は10時を打つ。1942年4月25日の美しい、なま暖かい春の夜である。
死んでゆく
誰か死んだのだ。誰だろう? 読教が聞こえる。これは私の葬式だ。しかし、喉の渇きを覚える。これは死人ではない。
「水を飲みたい」
ひとりが、私の頭を持ち上げて水差しを口に当てる。
「何か食べなくちゃ、二日間水しか飲まなかったよ」
何を言っているのだろう? もう二日も? 今日は何曜日だろう?
「月曜」
月曜日。私は金曜日に検挙された。おお、私の頭の何と重い事だろう。そして、水の何と冷たい事だろう。眠い。私を眠らせてくれ! 一滴の水が清らかな泉の面を波立たせた。
私が再び目を覚ますと、火曜日の夜である。私の頭の上に犬が首を傾げている。シェパードだ。
犬は美しい賢そうな眼で私を探るように見て、尋ねる。
「どこに住んでいた?」
おお、いや、それは犬ではない。その声はほかの者の声だ。私は長靴を目にする。その上は見えない。頭を上げようとすると、くらくらする。ああ、どうでも良い、私を眠らせてくれ。
水曜日
パンクラーツ警察監獄へ移送。フチークは担架に乗ったまま。長い廊下の奥の一室。好意を装うチェコ人が、ドイツ人の声の怒った質問を通訳する。
「あの女を知っているか?」
私は手の上に顎を乗せる。担架に面して、頬の広い少女が立っている。彼女は誇りを持ってまっすぐ立っている。頭を上げ、膨れてはいないが、犯しがたい面差しで。
「知らない」
私はどこかで彼女を一度見た事がある。多分、ペチェク会館のあの荒れた夜の一瞬に。
「だが、この女を君は知っているに違いない」
アニチカ・イラースコヴァ! おお、アニチカ、どうして君がここに来るような事になったのだろう? 私は君の名を言わなかった。私は君を知らない。いいかね、私は君を知らない。
「知らない」
「正気をとりもどせ!」
「知らない」
「ユリウス、同じ事です」とアニチカは言う。「同じ事です、誰かが私の名を出しました」
「誰が?」
「黙れ!」
彼らは彼女の答えを妨げ、私に手を伸ばそうとする彼女を突きのける。
アニチカ!
私にはそれ以上彼らの尋問は聞こえない。ふたりのSS隊員が私を監房に連れて帰る。彼らは邪険に担架を揺すぶり、縄からぶら下がる方が良いだろう、と笑いながら聞く。
木曜日
監房には、あと二人いる。年が離れているので、若い方は年長者をお父さんと呼んでいる。彼らは鉱山で働いていた様子だが、私には良く呑み込めない。
午後、監房のドアが開く。そして、静かに犬が入って来る。犬は私の枕元で止まり、再び私を探るように見る。そして、二足の重い長靴。一足はパンクラーツ刑務所所長のもの、もう一足はゲシュタポの共産党対策部部長のものだ。
「君たちは負けたのだよ。せめて自分だけ助かりたまえ。喋べれ!」
彼らは私に煙草を差し出す。私は欲しくない。
「バクサ夫妻の家ではどのくらい暮らした?」
バクサ夫妻の家? こんな事まで。誰が喋べったのだろう?
「良いかね、何もかも分かっているのだよ。すっかり言ってしまうが良いのだ!」
君たちが何もかも知っていたら、私がなぜこれ以上喋べらねばならぬのだ? 私は自分の生涯を空費しなかった。私はその終わりを台なしにはしないだろう。尋問は続く。
「分かったね? もうおしまいだよ。君たちの負けだ」
「負けたのは私だけです」
「君はまだコミューンの勝利を信じているのかね?」
「もちろん」
「まだ信じているって?」 思わず部長がドイツ語で聞く。「奴はまだロシアの勝利を信じているって?」
「もちろん、ほかの方法でこの戦争が終わる訳がない」
私は疲れている。血が深い傷から流れるに従って、意識が急速になくなっていく。
5月1日 早朝
監獄の塔が3時を打つ。はじめて私はそれをはっきりと聞く。検挙後、はじめて私はすっかり意識を回復した。しかし、体のいたるところが痛い。そして、息苦しい。私は死んでいくのだ。
死よ、お前はやって来るのに長い時間がかかった。かつて、私はお前と知り合いになるまで長年かかるだろうとたかを括っていた。私はまだまだ自由な人間としての生涯を生き、多く働き、多く愛し、歌い、そして世界中を歩き回れるだろうと思っていた。私はやっと一人前になったところで、まだまだ多くの力をもっていた。今では私には力がない。最後の時が近付きつつある。
私は生活を愛し、その美しさの為に戦った。人々よ、私はあなたたちを愛した。そして、あなたたちが私の愛に報いてくれたとき私は幸福だった。私はあなたたちが私を理解しなかったとき苦しんだ。私が傷つけた人は誰にせよ、私を許してくれたまえ。私が喜ばせた人は、私を忘れてくれたまえ。悲しみが、私の名に属する事が決してないように。これが、父よ、母よ、妹たちよ、そして君グスチナよ、君たち同志たちよ、私の愛したすべての人々に対する私の遺言である。もし涙が悲しみのごみを洗い去ってくれると思うなら、しばらく泣くがいい。しかし、私が喜びの為に生き、喜びの為に死んでいく事を忘れないで欲しい。私の墓の上に悲しみの天使を侍らせるような事があってはならない。
しかし、死は美しくしない。私は息をつまらせている。息ができない。少し水を飲んだら……。しかし、水差しの水はすっかりなくなっている。私からわずか6歩のところの房の隅の便器には水がたっぷりある。そこまで行きつくだけの力が私にあるだろうか?
私は腹ばいになって静かに這う。おお、とても静かに、まるで死の栄光のすべてがほかの人を起こさない事にかかっているかのように。とうとう行きつく。そして便器の底から水をむさぼり飲む。
私は手首の脈を探る。脈はぜんぜん打っていない。私の心臓は喉まで踊りあがり、とつぜん落ちる。長いあいだ落ちる。途中で私はカルリークの声を聞く。
「お父さん、お父さん、聞こえますか? かわいそうに断末魔ですよ」
朝になって医者がやって来た。
しかしこのすべてを私はずっとあとで知ったのである。
医者はやって来て、私を診察し、頭をふった。それから医務室に帰って、前の晩、私の名を書きこんだ死亡診断書を破り、専門家の自負を持って言った。
「あいつは馬のような体を持っている!」
二六七房
しかし、私はこれ以上のめない。私の裂けた歯茎は日曜のグラーシュ(ハンガリー料理、肉と野菜のシチュー)の中にある煮すぎたじゃがいもすら噛む事ができないし、私の腫れ上がった喉はどんなに小さな塊でも飲みこむ事を拒否する。
「グラーシュでさえ、この人はグラーシュでさえいらないと言っている」とカルリークは嘆いて、わたしの体の上で頭を悲しそうに振る。それから彼は、「お父さん」と公平に分け合ってから、私の分も半分のみこむ。
ああ、パンクラーツで1942年を暮らした者でないとグラーシュの本当の味は分からない。決して分からない! 胃袋が飢えの為うなり声を上げ、入浴のとき体が人間の皮をかぶった骸骨同然になっている事が分かり、仲間同士がお互いの食物を少なくとも目で盗みあい、乾燥野菜のむかつくような粥や、薄いトマト・ソースでさえご馳走に思われたこれらの最悪の日々に、雑役は週2回、木曜と日曜にじゃがいもを私たちの椀によそい、その上に肉ぎれの少し入ったグラーシュをひと匙かけてくれた。それは奇跡的においしかった。だが、おいしかったばかりでなく、それは人間生活、ゲシュタポ監獄の過酷な異常さのただ中で、文明的なもの、正常なものを思い出させる形のある何ものかであった。私たちはその事を夢中になって話した。ああ、日々の死の恐怖という香料によって味付けされたひと匙のおいしいグラーシュの達する事のできる価値の高さを誰が理解できよう!
ふた月たつと、私がグラーシュを断った時のカルリークの驚きが、私にも分かった。グラーシュさえ食べられないという事実ほど、私の近い死をはっきりと示すものはなかったのである。
その次の夜、カルリークは2時に起こされた。彼は出かける用意を5分のうちにしなければならなかった。生の終わり、ほかの監獄、強制収容所、あるいは絞首台に向かって行くのではなくて、まるでちょっと外出するように見えた。彼は私のわら布団の側に膝まづいて、私の首に手を回してキスした。すると、パンクラーツには感傷に浸る場所なんかないぞ、という制服を着た看守の叫び声が廊下に響いて、カルリークはドアから走り出、錠がガチャンと音を立てた。
そして、私たちは監房で二人だけになった。「お父さん」は、ヨゼフ・ペシェクという60才の教師で、検挙された教員仲間の長老である。彼は、解放後のチェコの学校の改革案を作成した事によって、ドイツ帝国に対する陰謀を企てたという理由で、私より85日前に検挙された。
「お父さん」は……
しかし、こうした事をみなどうして書けよう? それは骨である。一年間同じ監房にいる二人の人間! この間に「お父さん」という名のカッコがなくなり、年の違った二人の囚人が本当に父と子になり、私たちはお互いの話しぶりから気に入った表現や、癖になった身ぶりや、そして、声の調子まで自分の身につけた。今日では監房の中の私物のうちどれが彼のもので、どれが私のものであるか、何を彼がもってき、何を私が持って来たか、分からなくなっている!
彼は毎晩私と一緒に起きていて、死神が現われた時はいつでも白い湿布で追っ払ってくれた。彼は私の傷口から膿を取ってくれて、私のわら布団のまわりに漂っているいやな膿の匂いを気にしているそぶりも見せなかった。彼は最初の取り調べでズタズタになった私のシャツを洗い、繕い、どうにもならなくなった時は、自分のシャツを私に着せた。監獄の中庭で行われる朝の半時間の運動のとき危険を犯してまで小さな雛菊一本と草を一すべ摘んで持ってきてくれた。私が新たな取り調べに連れて行かれる時は、いつでも優しい眼で私を監房から送り出し、私が新たな傷を負って帰って来た時は、新しい湿布で包んでくれた。私が夜の取り調べに連れていかれた時、彼は、私が連れ帰られるまで寝入った事がなく、私をわら布団に寝かせて、毛布でしっぽりと包んでくれるのだった。
私たちの関係は最初の夜の取り調べの後こうして始まったが、それは私が再び起き上がれるようになって、息子として恩を返し始めてからも、少しも損なわれる事なく続いた。
共産主義者への監房検査は、ほかよりも頻繁だった。それは、好奇心からでもあった。看守たちは、がやがや話しながら、毛布を持ち上げ、傷口を吟味した。
プラーシェク(粉屋の見習い)という仇名の看守は、しょっ中訪れ、「赤い悪魔君、何か用はないかね?」と尋ねたりする。
数日後、プラーシェクは必要を見つけた。顔を剃る事だ。
同士ボチェクが連れて来られた。床屋だ。だが、ボチェクの手はふるえ、眼は涙でいっぱいになる。なぜなら、彼は私を死体と思い込んでいるからだ。私は彼を安心させる。
「さあ、しっかりして。ペチェク会館の拷問に耐えてきたんだもの、君の顔剃りに耐えられぬ事はないよ」
だが、体が弱っているので、二人ともときどき体を休めねばならない。彼も、私も。
妻だけが私の事を何も知らなかった。私のいる監房の階下の三つ四つ先の監房にひとりでいて、彼女は不安と希望の中に暮らしていたが、ある朝の半時間の運動の時間に隣の房の女が、私が死んだ、なんでも最初の取り調べで受けた傷がもとで監房で死んだそうよ、とささやいた。それから彼女は中庭を無我夢中で歩いた。世界が回って、女の看守が慰安代わりに拳骨を彼女の顔にくれて、正規な監獄生活のしるしである女囚たちの列の中に突き戻そうとしても、それを感じなかった。その日、泣く力もなく、監房の壁を見つめて座っている彼女の大きな優しい眼の前に、どんな場面が通りすぎた事だろう? あくる日彼女はほかの噂を聞いた。それは、私は殴られただけでは死ななかったが、苦痛から逃れる為に監房で縊死した、というのであった。
その間ずっと、私は貧弱なわら布団の上で転がり、毎晩根気良く壁の方を向いてグスチナのいちばん好きな歌を彼女に向かって歌っていた。私があれだけの熱情を歌の中に込めているのに、どうして彼女のわたしの声が聞こえなかったのだろう?
今では彼女は知っている。今では彼女はその歌を聞く事ができる。あの時より遠い房にいるのであるが。今では看守たちも267房では歌声がするという事実に慣れてしまって、もはやドアを叩いて沈黙を命じる事もしない。
267房は歌う。私は一生歌ってきた。もっとも激しい生き方をしているこの生涯の終わりに歌う事をやめる理由はない。そして、お父さんのペシェクは? 彼は異常な例で、歌う事がとても好きなのである。彼は声が悪く、音符を覚える耳もないのだが、それでいて美しい。献身的な愛情で歌を愛している。彼は歌う事にとても大きな喜びを見出しているので、音符を間違えて、イ調で歌うべきところをしつこくト調で歌っても、いっこう耳にさわらない。こうして、私たちは愉快であるにつけ、外の世界への憧れに胸が塞がるにつけ、歌を歌う。私たちは再び会えないかも知れぬ同志を見送る為に歌う。私たちは東部戦線からの良きニュースを祝って歌う。人間が幾時代にわたって歌ってき、人間である限りいつまでも歌うように、喜びの為に歌い、自分たちを慰める為に歌う。
太陽のないところに生活がないように、歌のないところに生活はない。そして、私たちはここでは歌が二重に要る。なぜなら、太陽は私たちのところまで届かないから。
400号室
今日は、1943年5月1日である。ちょうど私に好意を持っている看守が当直なので、私は物を書く事ができる。なんという幸福だろう! この日にまたしばらく共産主義者の編集長になって、新世界の戦闘勢力のメーデーのパレードの話を書けるとは!
だが、波打つ旗はなく、幾万幾十万の行進はなく、モスクワの赤の広場にあふれる幾百万の人々の海もない。
ここのパレードは、とても小さな形をとって行われる。
まず、隣の房から朝の挨拶に、ベートーベンから取った拍子をふたつ叩いてくる。それが今日はいつになく調子が荘重である。壁はいつもより高い調子で話す。
朝食を取る時は、もうすっかりパレード気分である。雑役たちは廊下で、コーヒー、パン、水を持って歩く。同志スコジェパは、丸いパンをいつもの二つでなしに三つ配って歩くが、これは彼のメーデーの挨拶なのである。用心深い人間が、動作であらわす挨拶なのである。握手代わりに我々の指はパンの下で固く触れる。話す事はできない。彼らは我々の眼の表情さえ逃すまいと見張っているのだから。しかし、唖だって指ではっきりと話す事ができるではないか!
私たちの房の窓の下の中庭に、女囚たちが朝の30分の運動に走り出る。私はテーブルの上にのぼって、窓ごしに下を見おろす。彼女たちはたぶん私に気づくだろう。気づいた。挨拶に握り拳を上にあげる。私も挨拶を返す。下の中庭は活気づいている。ほかの日に比べて本当に陽気である。女看守には見えない。あるいは見たくないのだろう。これだって今年のメーデーのパレードの一部なのである。
それから、私たちの運動の時間になる。私が運動の先頭に立つ。今日は5月1日である。諸君、看守が驚こうが、驚くまいが、何か新しい事を始めようではないか。最初の運動は大きな槌を振る事である。1、2、1、2。第二の運動は麦刈りである。少しの空想力さえあれば、同志たちは理解するだろう。槌と鎌。私はあたりを見回す。みなにこにこしており、元気に私の型どおりやっている。
房に帰る。9時。クレムリンの時計塔は10時。パレードが始まる。彼らはインターナショナルを歌っている。私たちは、ひとりぼっちではない。私たちは今、外で自由に歌っている人々に属している。彼らは戦っている。私たちが戦っているように。
♪囚われて冷たい壁の
うしろにいる仲間たちよ
君たちは我々とともにいる
よし我々の隊伍で歩めなくとも
そうだ、我々は君たちとともにいる。
しかし、ペチェク会館の「映画館」には楽しいものは何ひとつない。それは拷問室に通じる控え室で、君はそこから漏れる他人の叫び声や、うなり声を聞き、自分がどんな事に直面しなければならぬかと思う。君は人々が強く、健康な姿でそこへ入るのを見る。彼らは2、3時間の後には取り調べて打ちひしがれ、かたわにされて帰ってくる。入る時は力強い声が君にさようならを言うが、出てくる時その声は苦痛のため息が詰まり、しわがれて、熱っぽくなっている。時とすると、君はもっと悪い事を見る。君はひとりの人間が澄んだまっすぐな眼で入るのを見る。だが帰って来た時、彼は君の顔をまともによう見ない。彼は向こうの拷問室で弱い一瞬間、不決断、恐怖、そして、助かりたいという圧倒的な欲望の一瞬間を味わったのである。この事は、この同志が敵に売り、この恐ろしい経験を初めから味わわねばならぬ新しい犠牲者たちを、彼らが今日か明日連れて来る事を意味する。
良心の呵責に苦しむ人を見るのは、体が不具になった人を見るよりも悪い。もし君がここをのし歩く死によってぬぐわれ、君の感覚が復活によって刺激されているならば、言葉がなくとも、君は誰が動揺したか、誰が裏切ったか、誰が負けて仲間の働き手の中で重要さの一番少ない者の名を言っても良いという考えをしばらく抱いたかを、知っている。弱くなる者は哀れである。同志の命で贖って、彼らはどんな生涯を持つのだろう?
最初の驚きは奇妙でも不吉でもなかった。3週間ぶりの煙草は魅力に見えた。だが、それは吸って見て、持て余すほどのものだった。
第二の驚きは、四人の人間の変わりようだった。彼らはテーブルの後ろに腰を降ろし、書類を広げ、煙草に火を付ける。まるで、ここで事務を取っている普通の役人のように気軽に。しかし、私はこの人たちを知っている。少なくともそのうちの3人を知っている。彼らがゲシュタポの御用を勤めるなんてあり得ない。それとも? この3人まで? だって、そこにいる男は長らく組合と党の書記をしていた、粗野なところはあったが忠実で、私たちの間ではレネクという名で通っていたテリングルではないか? いや、こんな事はあり得ない! それから、そこにいる女は、髪の毛こそすっかり白くなっているが、まだ体がしゃんとしており、美しい、アンナ・ヴィコヴァーではないか? 彼女はしっかりした芯のある闘士だった。いや、こんな事はあり得ない! それからまたそこにいる男は、たしか北チェコの炭坑で左官をした事があり、党地方委員会書記だったヴァシェク・レゼクだ。私は彼を知っている。我々は北部でのあの激しい闘争をともにしたのだ。あの男が屈服するなどという事があり得ようか? いや、あり得ない! それにしても、彼はここで何をしているのだろう?
これらの問いに答えを見出せない間に、別の人々が現われた。ミレク、イェリーネク夫妻、フリート夫妻が連れて来られた。残念ながら、私はこれらの人々が私とともに逮捕されたのを知っている。しかし、ミレクの知識人工作を手伝っていたパヴェル・クロパーチェクまでここに来ているのはどういう訳だろう? 彼の事をミレクと私以外の誰が知っていたか? さらに、シュティフ博士。これは大変だ。医師グループがやられた事を意味する。だが、ミレクと私以外の誰がその事を知っていたか?
答えを見つけるのは難しい事ではなかった。しかし、それは残酷な打撃だった。ミレクが裏切った。ミレクが喋ったのだ! 今や、私は、彼らがどうして私の名を最初の夜知ったかを悟った。どうして、アニチカ・イラスコヴァがここに来ているかを理解した。なぜなら私は彼女の家でミレクに数回会ったからだ。今や、私は、なぜクロパーチェクとシュティフ博士がここへ来ているかを理解した。
彼は集団の中にいて、同じ思想を持った仲間たちに囲まれている時は強かった。しかし、一度隔離され、追及する敵の中にひとりでいると、彼はまったく力を失ってしまった。自分の事を考え始めて、何もかも失ってしまったのだ。そして、自分だけ助かる為には仲間たちを犠牲にし、臆病風に吹かれて裏切ってしまったのだ。
彼は、暗号を教えるより死んだ方が良いのだ、という事を忘れた。彼はアニチカを売った。彼を愛しているしっかりして、勇敢な少女リーダを売った。そして、私が死んだと思った時、彼はあとの全部を喋べったのだ。
卑怯者は、自分の命より大切なものを失う。彼は死んだも同然である。彼は自ら求めて仲間外れになった。彼は後に埋め合わせしようとしたが、二度と仲間に受け入れられなかった。
囚人と孤独とはよく混同されるが、それは大きな誤りである。囚人は孤独ではない。監獄はひとつの大きな集団である。どんな厳しい隔離も、人を仲間から引き離す事はできない。彼が自ら求めて仲間外れにならぬ限り。
奴隷の友愛には圧力が加えられるが、圧力はかえってこの友愛を強化し、緊密にし、敏感にする。友愛は壁を浸透する。壁は生き、話し、合図をする。友愛は、全監房を抱擁する。運動に出ている時は、言葉ひとつ、あるいは小さな動作ひとつで、ニュースを伝えたり、人命を救うのに充分である。
四〇〇号室は、共産党員の為の、映画館の支所である。ここには、警視庁から派遣されたチェコの巡査部長と平巡査が詰めている。通訳として、ゲシュタポに仕えている。
囚人の中には、強さを持ち続ける者もいた。巡査の中にも、こういう人種がいた。彼らはゲシュタポの前では囚人を殴ったが、四〇〇号室ではパンのかけらをくれた。検挙隊の中では君の家の貴重品を盗んだが、四〇〇号室では煙草をくれた。
保身を第一に考える巡査もいた。彼らは、その時々の政治的天候の敏感なバロメーターであった。彼らが職務に熱心な時は、ドイツ軍の遠征が順調に進んでいる事が分かった。バカに愛想がよく、囚人と話をするようになれば、スターリングラードで退却した事が知れた。
人殺しと呼ぶほかない人種もいた。彼らはゲシュタポがいたたまれずに逃げ出したほど、同国人をひどく拷問した。快楽の為に拷問し虐殺し、持って生まれた残忍さの為に、我々の歯を折り、鼓膜を破り、眼を突き、股を蹴った。
人殺しと同じテーブルに、「人間」と呼ぶべき人々もいた。囚人たちを保護する為に獄則を利用し、囚人仲間の結束を助けた。彼らの偉大さは、彼らが共産主義者でないだけによけいに際立つ。それどころか、彼らは警察官として、戦前は共産活動の妨害をしていた。しかし、彼らは、我々が占領者に対して戦うのを見て、共産主義が民族に対して持つ意義を悟ったのだ。
イェリーネク夫妻
ヨゼフとマリエ、夫は車掌、妻は家政婦。君に、彼らのアパートを見せたい。質素だが、磨きのかかった家具、そして信じられないまでの清潔さ。ここにはマリエの全精神が込められており、ほかの世界の事など彼女は何も知らないと思われるかも知れない。しかし、彼女は共産党で長いあいだ活動していた。彼らはどちらも献身的に、そして静かに働いた。外国の侵略が重い任務を彼らに課した時は、決して尻ごみしなかった。
1943年5月19日
今夜彼らは、私のグスチナをポーランドへ「労働」に連れて行く。(実際は、ベルリン北部の婦人専用収容所ラヴェンスブリュックにて、解放まで収容)
苛酷な労働に、病気。彼女にはあとわずか三ヵ月の命しかないだろう。私は、このレポートを書き続けている。しかし、今日は書けない。私の頭も心も、良き伴侶であったグスチナの事でいっぱいである。
毎夜、私は彼女に聞かすつもりで、彼女のいちばん好きな歌をうたった。パルチザン闘争の湧き立つ栄えある物語を、ささやく草原の青みを帯びた草の歌を、夫とともに自由の為に戦ったコサックの乙女の歌を、その勇ましさを称えた歌を、そして、いかにある戦闘の後で彼女が倒れたまま地上から立ち上がらなかったかの歌を。
見て下さい、ここに私の戦いの伴侶がいる! あの小さな体、あのくっきりと刻まれた顔に何と大きな力が潜んでいる事か! あの大きな子供っぽい眼に、どんな優しさがこもっている事か! 不断の闘争と度々の不在が、私たちを最初の愛撫と最初の結合の燃えるような瞬間を百回も味わう永遠の恋人にした。私たちのふたつの心臓に鼓動するのは、いつでもひとつの脈であり、私たちふたりが幸福の瞬間、不安、興奮、あるいは悲しみの時に呼吸するのはひとつの呼吸である。
長年、私たちは一緒に活動し、仲間同士として助け合ってきた。長年、彼女は私の最初の読者であり、最初の批評家であった。彼女の優しい眼差しを自分の上に感じない時に書く事は、私には困難であった。長年、私たちは闘争の中で手を取り合って立ってきた。そういう闘争は、私たちの生活では少なくなかった。私たちは多くの試練に出くわしたが、同時に多くの喜びも味わった。なぜなら、私たちは貧しき者の富、私たちの中にある富によって豊かだったのである。
グスチナ? ごらん、これがグスチナだ。
戒厳令の時、去年の六月中旬の事であった。彼女は、私たちが捕まってから六週間目に、私が死んだといういろいろの噂に対して、監房の中でひとり考えあぐんだあの恐ろしい日々の後に、始めて私の姿を見た。彼らは、私を軟化させる為に彼女を呼んだのだ。
「彼を説得したまえ」 と部長は、私たちを対面させながら、彼女に言った。「手数をかけないよう説得したまえ。もし彼が自分の事を考えないなら、せめて君の事を考えるようにさせたまえ。一時間上げるから考えてみたまえ。それでもまだ彼が意地を張るなら、今夜銃殺する。二人ともだ」
彼女は私を眼で愛撫し、簡単に答えた。
「警部さん、そんな事は私には何の脅しにもなりません。私の最後のお願いです。もしあの人を処刑するなら、私も一緒に処刑して下さい」
ごらん、これが私のグスチナだ! 限りない愛と、芯の強さ。
彼らは私たちの命を奪う事ができる。ねえ、グスチナよ、だが私たちの愛や誇りを奪う事はできない。人々よ、これらすべての苦悩が過ぎ去った後で、私たちがもし出会うような事があれば、どんな生活をするか、想像できますか? 自由と創造によって美しい、解放された生活の中で会えたならば? 私たちが望み、その為にこのように懸命に働き、そして、その為に今死んでゆく大業がなし遂げられた時に? たとえ死んでも、私たちは諸君の大きな幸福のかけらの中に生き続けるだろう。なぜなら、私たちはその中に私たちの命を投資したのだから。自分の命と別れる事は辛いが、それは私たちに喜びを与える。
しかし、彼らは私たちにさようならを言う事も、抱擁する事も、そして、手を握る事さえ許さなかった。パンクラーツとカレル広場の間を連絡する囚人の集団のみが、私たちに互いの運命に関するときおりのニュースをもたらす。私たちがおそらく二度と相見る事がない事を、グスチナよ、君は知っている。そして、私も知っている。それでも、私は遠くから呼ぶ君の声を聞く。さようなら、愛する人よ、また会うまで。
また会うまで、私のグスチナ!
私の遺書
私は多くの文章を書いた。その多くは、過ぎ行く日に属しているもので、忘れられて良い。しかし、中には生命に属するものもある。私はそれを親友のラージャ・シュトルが出版してくれる事を望む。
(シュトルはチェコ共産党中央委員の文化指導者。戦後、シュトルとグスチナの共同でフチーク選集が編まれ、1960時で11巻まで出された)
ヤン・ネルダは、我々の中の最大の詩人である。ジャーナリストとしての一面は、詩作の妨げになったと思われがちである。しかし、その素晴らしい作品を作り得たのは、彼がジャーナリストだったからだ。ジャーナリズムは、人を疲れさせ、気をそらせもするが、その反面読者と直接つながらせ、いかに詩を作るかさえ教える。もちろん、それはネルダのように誠実なジャーナリストである場合に限る。
私は同志たちの手を堅く握る。そして、繰り返す。私たちは幸福の為に生きた。そして、幸福の為に戦いに行き、幸福の為に死んでゆく。だから、悲しみが私たちの名と結びつく事が決してないように。
1943年5月22日
予審判事は、訴状を作成した。あとは裁判と、判決待ち。5ヵ月はかかる。その間に、一切が変わる場合がある。外の出来事が、我々の終わりを早める可能性もある。それは、戦争と希望との競争である。ファシズムの死と、私の死と、どちらが先に来るかの競争。
私はよく、戦争の最後の瞬間に最後の弾丸で心臓を撃ち抜かれる最後の兵士である事は、どんなに悲愴であるだろうと考えた。しかし、この競争下では、誰かが最後に倒れる兵士にならないといけない。もし私が、この最後に倒れる人間になれると分かれば、私は今でも出かけるだろう。
イェリーネク夫妻は、普段なら、この人たちの内に英雄を見い出す事はなかっただろう。逮捕された時、彼らは両手を頭の上にあげて並んで立っていた。彼女の眼はゲシュタポが彼女の模範的なアパートを5分の内にめちゃくちゃにしたのを見て、いくらか怯えたようだった。それから彼女は顔を夫の方に向けて聞いた。
「ペパ(=ヨゼフ)、いったいどうなるの?」
彼は無口で、言葉がすぐ出ない方だった。そして、喋べると興奮した。だが、今は静かにすらすらと答えた。
「死にに行くのだよ、マーニャ(=マリエ)」
彼女は悲鳴を上げなかったし、よろめきもしなかった。美しい動作で、絶えず向けられているピストルの銃口の前で右手をおろし、彼の手をしかとつかんだ。この事で二人とも顔に最初の打撃を受けた。彼女は頬をふき、闖入者たちをいくらか意外だといった顔つきで見て、ほとんど滑稽な調子でいった。
「こんな可愛い若い人たちが」 と彼女は声の調子を上げていった。「こんな可愛い人たちが、こんな乱暴者になるなんて」
彼女は彼らを正確に評価した。数時間後、彼らは、「取り調べる」警部の部屋から、殴られて失神せんばかりの彼女を担ぎ出した。しかし、彼らは彼女から何物も叩き出す事はできなかった。その時も、それから後も、決して。
どんなにたびたびペパは、手首を足首に括りつけられて、ひっきりなしに殴られた事か。
私が検挙前に知っていた彼の妻は、感じやすくて哀れみ深かった。しかし、ゲシュタポに捕えられてからの全期間に、私は彼女の眼に一滴の涙も見かけなかった。
彼女の最後の言葉はこうだ。「ほかの人たちにお伝え下さい。私の運命によって尻ごみする人がないように。私は労働者として為すべき事をし、その為に死んでゆくのです」
彼女は「家政婦」に過ぎなかった。古典の教養に乏しく、次の言葉を知らなかった。
「巡礼よ、スパルタ人たちに伝えよ。われら掟に従いて死に、ここに眠る(=BC480、テルモピレーの碑)」
リーダ
バクサ夫妻のアパートで、私は、ヨシカとリーダというふたりの少女に出会った。リーダはまだ子供子供していたが、驚いた事にもうすぐ19才だった。演劇好きで、少女らしく短気で、末っ子の常として甘やかされていた。
当事、私はびっこを引いた初老の男に扮装していたが、外出の際にリーダを伴った。すると、誰もがリーダを見て、初老の男には眼をくれなかった。自然の成り行きで、彼女は私のサポーター役になった。
彼女は自分の役割を思い煩う事なく、その仕事を楽しんでいた。それは冒険の味がした。彼女には、それだけで充分だった。
私はリーダには多くを語らなかった。知る事が少ないほど、捕われた時に、自分を守りやすい。しかし、リーダは急速に発展した。そして、レポートの配達のみならず、責任ある仕事まで任されるようになった。
活動の中で、彼女はミレクと知り合った。ふたりの中で、愛が成長した。
1942年2月、リーダは中央委員会の決議によって入党を許された。
リーダは重要な仕事を任された。さしせまる危険にさらされている働き手たちに警告するという、この上なく危険な仕事をこなした。指導部や隠れ家が危なくなると、リーダはうなぎのようにすり抜けて、うまく処理した。
ミレクのお喋べりで、ゲシュタポは彼女に注意を払うようになった。彼女は、バクサ夫妻の逃亡の手引きをした事をつかまれた。しかし、彼女は、なにか非合法な事をやったとは夢にも思わぬ気軽な少女の役を演じて、難を逃れた。
党に対する彼女の義務は変わらなかった。彼女は与えられた任務をすばやく、献身的に遂行した。彼女は志願して、パンクラーツの女監の雑役になった。そして、何十という人々が、彼女の届けるレポートによって検挙を免れた。一年近くこの仕事が続いて、ひとつのレポートから足が着いた。
彼女は、私たちとともにドイツへ裁判に行く。彼女は若い。どうか、彼女を見失わないようにして欲しい。
(リーダ・プラハーは健在で、プラハ国民劇場の女優である)
私の警部
ロシアの活動家は、モスクワ、ペテルブルグ、オデッサと、場所を変える事ができた。しかし、ここには、住民の半数が君を知っていて、敵のスパイが群れているプラハしかない。
2−A1部には、フリードリッヒ、ツァンデル、ベームの3人がいる。
ツァンデルは勤勉だが、金に汚い。プラハからベルリン勤務になったが、本人の希望で戻して貰った。プラハの方が、金を増やす機会が多いのだ。彼の手中に落ちた者は災難であるが、家に銀行通帳か有価証券をもっている者こそ、二重の災難である。その人間はまもなく死ぬ。なぜなら、銀行通帳と有価証券はツァンデルの執心の的であるから。
フリードリッヒの執心は、屍である。彼は誰であろうが無罪を認めない。彼の部屋の敷居をまたいだ者は誰でも有罪だ。彼は女たちに、その夫が死んだと告げるのが好きだ。机の引き出しから七つの骨壷を出して、取り調べ中の者に見せて言う。「この七人はわしがこの手で殴り殺してやった。お前は八人目だよ」
彼が特に好きなのは、女をいじめる事である。
ベームは、金や屍には執着がない。彼は立身出世を夢見ている。彼は巨大なスパイ網を作り上げた。その多くの犬を連れた狩人となって、大きな狩りをやる。ある時は、市電の200人の車掌と運転手を一斉検挙して、プラハの交通を麻痺させた。それから、無関係な150人を釈放して、150の家族から親切な人として感謝された。
ステッキと鉄棒のほかに、脅しや口説きも取り調べの道具だった。最初の夜のほかは、一度も私を拷問しなかった。必要な時は、ほかの誰かにやらせた。
1942年の戒厳令
5月27日、ゲシュタポ長官兼チェコ総督ハインドリッヒが、在英チェコ人のパラシュート部隊によって暗殺された。そして、プラハには戒厳令が敷かれた。
パンクラーツからペチェク会館への行き帰りの道は、幾千の囚人にとって受難の道となる。護送車で見張りをするSS隊員たちは「ハインドリッヒの敵討ち」をする。護送車が1キロも行かないうちに、ピストルの尻で殴られた幾十人の囚人の顔や口から血が流れる。私と一緒のクルマに乗った者は楽である。というのは、私の顎ひげがSSのいたずらの対象になって、ほかの乗客たちを殴る時間があまりないからだ。
50人、100人、200人の人間が一瞬のうちに手足を括られ、トラックに乗せられ、屠殺場行きの家畜のようにコビリシの大衆処刑場に連れて行く。彼らはどういう罪を着せられたのか? 第一に、彼らを罪にする何ものも発見できなかったという事である。彼らは検挙されたが、大物たちの誰とも接点がなかった。彼らにはこれ以上の取り調べをする必要がない。それで、処刑しても良いという訳である。
ある婦人が非合法パンフレットを配布した疑いで6ヶ月前に検挙された。彼女はそれを認めなかったし、何の証拠もなかった。それでも彼らは、彼女の兄弟姉妹、姉妹の夫たちと兄弟の妻たちの全員を処刑しようとしている。
その夜、私は取り調べから遅く帰った。階下の壁際に、ヴラディスラフ・ヴァンチュラが足元に身の回りの包みを置いて立っている。私はそれが何を意味するか知っている。そして、彼も知っている。私たちはしばし手を固く握る。半時間後、彼らは彼の名を呼んだ。
数日後、同じ壁に昨年検挙された我々の勇ましい戦士であるミロシュ・クラスニーが立っている。拷問によっても、監禁によっても、少しも打ちひしがれていない。彼はそばの看守に何か話している。
「こんな事はあなた方には何の助けにもなりませんよ。私たちの仲間はまだこれからたくさん倒れてゆくでしょうが、結局あなた方の負けです」
屍は積み重なっていく。それはもはや何十でも何百でもなく、何千という数に上る。そして、この恐怖の中で人間は?
生きている。
それは、信じられない事である。しかし、人々はまだ生きて、食べ、眠り、恋をし、働き、そして、死とは関係のない多くの事を考えている。
戒厳令の最中に、警部は私をブラニークへ連れ出した。美しい六月は、シナノキと遅咲きのアカシアの花に匂っていた。日曜の夕方で、市電の終点に通ずる国道はピクニック帰りの人々の流れで溢れていた。
私は窓から、通りや店のショーウインド、花売りスタンド、通行人の群や女たちを見る事ができた。私はいつか、美しい脚を九対数える事ができれば、その日死刑に処せられる事はないと自分に言い聞かせた事がある。その時、私は脚を見、注意深く研究し、脚にとても興味をもって選んだり、除外したりした。私の命がそのいかんに掛かっている事などはすっかり忘れて、まるで問題なのは命ではなく、脚の線であるかのようだった。

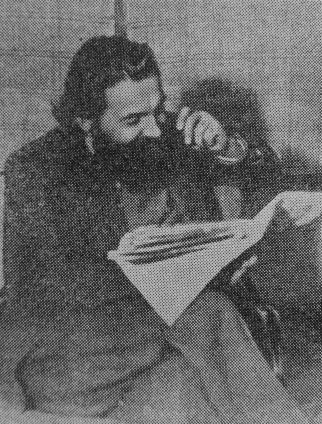
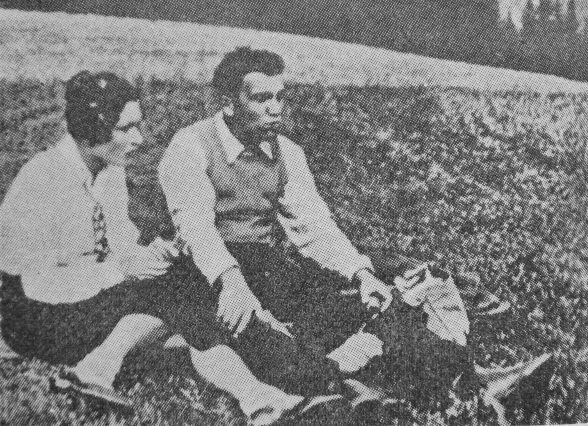
寸評
多くの国で、共産主義は、反国、反体制活動と重なります。
しかし、1940年代のチェコスロバキアでは、奇跡的に、愛国と、反ナチと、民族解放運動と共産主義とが重なったのです。この情熱は、本物です。
フチークは、スターリンによる解放を信じて、亡くなりました。スターリンは恐怖政治で、ロシアにおいても否定されています。それでも、フチークの美しさは変わりません。拷問や監禁に耐える姿が、皮肉にも、スターリン体制を批判するものとなっているのです。
日本は敗戦国=悪者ですが、ヒロシマの被爆者、ナガサキの被爆者については、世界中の誰もが悪くは言いません。平和な日常を破壊された、戦争の犠牲者として、誰もが同情を寄せてくれます。フチークもそうです。戦争と、政治闘争の犠牲者として、永遠に哀悼を捧げられるべきです。