
フレデリック・ダグラス
ある黒人奴隷の半生
フレデリック・ダグラス、刈田元司、筑摩書房、1963。
生いたち
私は、メリーランド州ヒルズボロ近郊タカホーに生まれた。年齢については、正確には知らない。多くの奴隷は、馬がそうであるのと同様、自分の年齢を知らない。このように奴隷を無知にしておく事が、主人たちの希望なのだ。
母はハリエット・ベイリーと名乗った。黒人で、彼女の両親も黒人だった。私の父は白人だった。しかし、噂である。私がまだ幼いうちに、母親から引き離されてしまった。これは、普通の習慣だ。奴隷の子供は12才未満で、遠い農場に貸し出し、畑仕事のできなくなった老婆に世話させるというのが一般的だった。何の為に、こういう事が行われるのか分からない。互いの愛情を打ち砕く為というなら、その目的は達せられている。
私は今まで、母には4、5回しか会っていない。母の雇い主はスチュアート氏で、うちから12マイル離れていた。奴隷は日中は働かねばならず、休日はなかった。だから、私は昼間、母の顔を見た事がない。母は夜しか来なかった。私を寝かしつけると、翌朝にはいなかった。私が7才の頃、母は亡くなった。病気中も、臨終も、葬式の時も、私はそばにいる事を許されなかった。
母は私に、父の事は何も言わずに亡くなった。だから、私の主人が父であるという噂の真偽は確かめようがない。だが、奴隷の子供は奴隷であるというのが決まりであり、法律である。だから、多くの奴隷所有者は、奴隷に対して、主人であり父親であるという事が珍しくない。
その例は多く、しかも、息子である奴隷は、他の奴隷よりも辛い目に合うという事は、言っておくべき事だ。まず第一に、女主人の目の仇にされる。女主人は、奴隷に手落ちはないかと、絶えず目を光らせている。めったに喜ぶ事はなく、機嫌が良くなる時は、奴隷が鞭に打たれる時だけだ。ことに、夫の血を引く奴隷が鞭打たれている時は溜飲を下げる。主人は、妻に対する気兼ねから、こういう奴隷を売り飛ばす場合が多い。血を分けた息子を売り飛ばすとは、残酷と思われるが、そうでもない。さもないと、主人みずから息子を鞭打ち、裸の背中に血が出るまでしないと、えこひいきと非難されるからだ。
こういう新種の奴隷はおびただしく生まれている。アフリカから来たばかりの奴隷とは、まったく顔付きの違う奴隷が南部に生まれている。そして、同じように体を縛られている。
最初の主人はアンソニーで、30人の奴隷を抱え、監督の名はプラマーといった。プラマーは悪態つきのサディストで、鞭と棍棒を常備し、一度は、女たちの頭をめった切りにした事がある。さすがの主人も腹を立てて怒ったが、その主人も決して人情家ではなかった。
主人は、奴隷所有に馴れて、心の頑なになった残酷な人だった。ある朝、私は叔母の悲鳴で目を覚ました。主人は叔母を根太に縛り、裸の背中を鞭打ち、一面に血が流れていた。犠牲者が叫び、涙を流し、祈っても、主人の心を溶かす事はできなかった。悲鳴が大きくなるほど、鞭は鳴り、血がさかんに噴き出すところを、鞭は狙った。彼は彼女に、悲鳴を上げさせる為に鞭打ち、黙らせる為に鞭打った。疲れるまで、鞭は止まなかった。このような暴行を始めて目撃した時の事を、私はありありと覚えている。ほんの子供だったが、忘れる事はない。
ヘスター叔母は、美人だった。物腰はしとやかで上品で、周辺の黒人も白人も含めて、容姿でかなう者はなかった。ロイド牧場のネッドという奴隷が、ヘスターに関心を寄せていた。主人はヘスターに夜間外出を許さず、ネッドと一緒に居るところを見たら承知しないと警告していた。
ヘスターは、ネッドと一緒に居るところを見つかった。それが、叔母の純潔を守る為にしたのでない事は、主人を知る人にとっては自明だ。主人は彼女を納屋に連れ込み、腰から上を丸裸にした。そして、腰掛けに座らせ、両手は縛って天井から吊るした。主人は鞭をふるい、温かい血が床にしたたり、彼女の絹を裂くような悲鳴と、主人の呪いの言葉とが混じり合った。私は便所に隠れて、出る事ができなかった。
奴隷の生活
私は、ロイド大佐の農園にいた。そこで取れるのは、タバコ、とうもろこし、小麦。ボルチモアへは、大型帆船が往復していた。
本部農場には400人の奴隷がいて、近くの農場にはさらに多くの奴隷がいた。監督は20人。逃亡したり、反抗したりした奴隷は、鞭打たれ、よそへ売り飛ばされた。
奴隷は月に、8ポンドの豚肉、36リットルの麦を受けた。年一回支給される服は、シャツ2枚、ズボン1足、上着1枚。10才までの子供たちは、ほとんど裸で過ごした。
ベッドはなく、毛布が与えられたが、それよりも睡眠不足に悩まされた。日中は畑仕事で、炊事、洗濯、繕いは、夜中に回される。しかも、道具の手入れもしなければならない。睡眠は不足勝ちだった。朝はラッパで起こされた。起きない者には、監督が鞭の雨を降らせた。
セピア氏の残酷は筋金入りだった。母親の許しを願って泣き叫ぶ子供の前で、だらだらと血を流させ、半時間もひとりの女を鞭打ち続けるのを見た事がある。残虐さに快感を感じているかのようだった。日の出から日没まで、彼は畑にいて、怒鳴り散らし、鞭をふるい続けた。
セピアの後任にホプキンズが来た。彼は鞭で殴りはしたが、快感を感じているようには見えなかった。それだけで、良い人だと言われた。
本部農場は、よその農場より優秀だと思われていた。それで、ちょっとした用で本部農場へ行く奴隷は、大声で歌いながら歩いた。
奴隷たちの歌には、自由への願いが込められていた。北部で、奴隷の歌には幸福感があると評する人に出会って、私は驚く。奴隷が歌うのは、多くは不幸な時だ。心の痛みが涙によって和らげられるように、奴隷は歌によって慰められる。
主人のこと
ロイド大佐の農場には、各地から見物客が来た。農園では、リンゴやオレンジが栽培されていた。それは、子供はもちろん、大人にとっても誘惑の種だった。大佐は様々な策を練った末に、塀にタールを塗った。それ以降、体にタールを付けた奴隷は鞭打たれた。奴隷は、鞭だけでなく、タールを恐れるようになった。
大佐は馬にも凝った。馬の世話はバーニー親子に一任された。これは生易しい仕事ではなかった。大佐は時には、60才のバーニー老人を30回も鞭打った。大佐には3人の息子と、3人の娘婿がいた。みなが鞭打ちを楽しみにしていた。ひと打ちで、奴隷の背中にはみみず腫れが盛り上がるのだ。
奴隷の総数は千人はいた。多くは、大佐の顔も知らなかった。ある時、大佐は公道でひとりの奴隷に話しかけた。「お前はどこの奴隷だね」「ロイド大佐です」「大佐はお前を優しく扱ってくれるかね」「とんでもねえです、旦那」「食べ物の方は充分かね」「今のところは充分です、旦那」
気の毒な奴隷は、主人の悪口を言った罪で、よそへ売り飛ばされる羽目になった。何の前触れもなく、家族からも、友人からも、永久に引き離されたのだ。北部の人が、奴隷の境遇について尋ねた時、ほとんど例外なしに、自分は満足している、主人は親切だ、という答えが返って来るのは、この為である。農園主の中には、奴隷の中にスパイを放つ者もいる。こういう事が重なって、奴隷たちは、もの言わぬが利口、という格言を作った。
奴隷たちも人の子で、よその農園主よりは自分の主人の方が良いと思い込みたがる。そして、よその奴隷たちと出会った場合、銘々がうちの主人は親切だと言い争いをする事が珍しくない。
ロイド農場の奴隷がジェプソン農場の奴隷と顔を合わせると、喧嘩別れをしない事はまずない。自分の主人は金持ちだ、人格高潔だ、果ては、うちの主人は相手の主人を鞭打つ事ができると言い、殴り合いの喧嘩になる。
監督の非道
ホプキンズ氏は、長く続かなかった。後任のゴア氏は、残酷で、陰険で、野心家だった。奴隷のどんな些細な目付きでさえ、生意気だと決め付けて、いじめ抜く事ができた。口答えは許されず、言い訳さえ許されなかった。「監督たる者は、過ちを認めるよりは、十人の奴隷を鞭打った方が良い」 この金言に忠実な監督だった。
まじめに働いても、ゴア氏に睨まれたら罰を受けた。奴隷たちは、彼の姿を見るだけで怯えた。その甲高い声を聞くだけで、奴隷たちは恐怖と戦慄に身舞われた。
ゴアはかつて、デンビーという名の奴隷を鞭打とうとした。デンビーは3回鞭を喰らうや、逃げて川に飛び込んで、出ようとしなかった。ゴアは3度呼んで出なかったら撃ち殺すと脅した。一度目、デンビーは川の中に立っていた。二度目、三度目、デンビーは動かなかった。ただ、川の中に立ったままだった。ゴアは大佐にも相談せず、デンビーの額に狙いをつけた。次の瞬間、デンビーは見えなくなった。彼の体は沈み、赤い血が川面に浮かんだ。
農園中に、恐怖の戦慄が走った。ゴアは大佐に呼ばれ、理由を聞かれた。その答えは、デンビーが手に負えなくなった、というものだった。デンビーがほかの奴隷に危険な手本を示し、このまま放置すれば農園の秩序は保てなくなるだろうと。この答えは完璧だった。彼の地位は保たれた。監督としての名声は、よその土地にまでとどろいた。この事件は、多くの奴隷の面前で行われたのに、彼らは訴える事もできず、証拠を並べる事もできなかった。
メリーランド州では、奴隷を殺しても罪にならなかった。マイケル農園のトマス・ラン氏はふたりの黒人を殺した。そのうち一人は、斧で頭を砕いた。彼は笑いながら言った。「俺はこの国の恩人だ、みんながこうすれば畜生と縁が切れるのだ」
ジャイルズ・ヒック氏の妻は、私の妻の従姉妹の15才の娘を殺した。その晩、ヒックス夫人は、赤ん坊の子守りを娘に命じた。しかし、娘は、六日続けて休息を取っていなかったので居眠りしてしまった。赤ん坊が泣き出しても、うとうとと眠っていた。ヒックス夫人は同じ部屋にいた。婦人は娘が動かないのを見ると、ベッドから降り、樫の棒を掴み、娘の顔や体をかまわず叩いた。鼻が砕かれ、肋骨を折り、娘は3時間後に果てた。すぐ埋められたが、検死官が来て、掘り出された。死因は、激しく殴打された為だった。
事件は、地域にセンセーションを起こした。逮捕令状も出された。しかし、逮捕はされなかった。夫人は、出廷さえ免れた。
ロイド農園の奴隷は、食糧不足を補う為、海岸に出て牡蠣を取る習慣があった。これは、大目に見られていた。たまたま、ひとりの老人が、境界を越え、ボンドリー氏の土地に入った。ボンドリー氏は、この老人を撃ち殺した。翌日、ボンドリー氏がロイド氏を訪問した。謝罪か、賠償かは、よく分からない。事件はうやむやにされ、善後策さえなかった。白人の少年たちさえ、こう言った。「黒んぼを殺しても半セントにもならない」
ボルチモアへ行く
奴隷の子供には、暇はたくさんあった。牛追い、家族の使い走り、ロイド大佐の撃ち落した鳥の回収。息子のロイドとは、仲良しになった。彼は私を庇い、お菓子も分けてくれた。
ロイド大佐は、私を鞭打ちはしなかった。しかし、空腹や寒さには泣かされた。靴も、ズボンも、上着もなく、真冬でもシャツ一枚だった。とうもろこしの袋がなかったら、凍えて死んだに違いない。子供時代からの霜焼けで、足には大きなひび割れができている。この原稿を書いているペンが、その割れ目に入る。
食事はとうもろこし粥で、桶に入れて運ばれ、十数人にまとめて与えられた。年長者が良い場所を占領した。満腹して桶を離れる者はいなかった。
ロイド大佐の父が、私を娘婿の兄弟のオールド氏の農場で働かせると決めた。そこはボルチモアで、八つの時だった。出発までの三日間は、生涯最高の日々だった。
ボルチモアの人は清潔だと聞かされていた。だから、私は毎日川で垢を落とした。子供を家庭に結びつける絆が、私にはまったくなかった。いとこのトムは、ボルチモアの魅力を雄弁に語った。この世に、それ以上の場所はないように思われた。
マイルズ川でボルチモアに向かった。帆船には、多くの羊が同居していた。ボルチモアの街並は、本部農場よりも堂々としていた。
案内された先は、農園ではなく、造船所近くの通りに面した普通の家だった。オールド夫妻と、小さな息子のトマスとが私を迎えた。この時、私は今まで見た事のないものを目にした。それは、実に優しい情感をたたえて微笑している白人の顔であった。新しい女主人ソフィア・オールドの顔だった。私の魂を恍惚感が貫いて流れた。小さいトマスに、これがあなたのフレディと紹介された。
新しい主人
新しい女主人は、世にも優しい心と美しい感情の持ち主だった。私以前に、奴隷というものを使った事がなかった。結婚前は機織り仕事をしていた。私は彼女の善良さに驚いた。どう振る舞って良いのか分からなかった。奴隷特有の、はいつくばった服従では、彼女の好意は得られなかった。そんな態度に、彼女は戸惑った。その顔をまともに見ても、彼女はそれを生意気とも不作法とも思わなかった。彼女と会って、楽しい気持ちにならずに別れた者はなかった。その顔は天使、その声は音楽だった。
しかし、悲しい事に、その優しい心は短い期間しか続かなかった。悪い毒素がその中にあって、それがやがて悪魔的な働きを始めた。奴隷制度に影響されて、明るかった目は、狂暴の為に赤くなり、美しい声は、耳障りな声とかわり、天使の顔も悪魔の顔となった。
夫人ははじめ、私に文字を教えた。それを知って、オールド氏は禁じた。彼は言った。「黒んぼに少しを与えたら多くを望むようになる。黒んぼは命令に従いさえすれば良い。黒んぼに文字を教えたら、おしまいだ。もう使えない。本人にとっても不幸だ」
この言葉は私の心の深くに染み通った。私はこの教訓を嬉しく思った。先生なしで勉強するのは困難だが、どんな労苦を払っても勉強しようと決心した。
ボルチモアとて、南部である。それでも、田舎と都会とではまるで違っていた。都会の奴隷は、ほとんど自由人で、食事も服装もずっと上等だった。農園では当たり前の残虐さもなく、礼節と外聞がゆき渡っている。たまに奴隷に悲鳴を上げさせるのは、評判の乱暴者である。奴隷に満足に食事を与えない事は、恥とされた。
しかし、都会にも例外はあった。向かい通りのハミルトン夫妻は、ヘンリエッタ20才と、メアリ14才のふたりの奴隷を抱えていた。ふたりとも、いつも傷付き、痩せ衰えていた。ふたりを眺めて平気でいられる人は、その心は石よりも固い。メアリの頭も首も肩も、いつも鞭で傷付いていた。私は用で、ほとんど毎日ハミルトン氏の家に出入りした。夫人は、重い鞭を片時も手放さなかった。一日のうち一時間でも、ふたりの娘が血を流さずに済む事はなかった。夫人の前を通る度に、「もっと早く動くんだよ、ニガー!」と叫んでは鞭が降りた。「さあ、ニガ―、これでも喰らえ」「私が動かしてやるよ」と鞭が続く。加えて、飢餓。私は、メアリーが、通りに捨てられた残飯を豚と争って食べているのを見た事がある。メアリーは本名よりも、はじかれ娘と呼ばれていた。
文字を習う
私はオールド氏のところにいた7年で文字を覚えた。優しかった女主人は、教えるのを止めたばかりでなく、誰かほかの人が教えるのにさえ眉をしかめるようになった。この邪悪な精神は、彼女は始めは持っていなかった。私を野獣のように扱うには、訓練が必要だった。
彼女は優しく、親切な女性だった。奴隷制度について、何も知らなかった。しかし、奴隷制度は私にとって有害であったように、彼女にとっても有害であった。始め、彼女は敬虔な、暖かい、優しい女性だった。彼女が涙を流さない人の苦しみはなかった。飢えたる者にはパンを、裸の者には服を、悲しむ者には慰めを与えた。
奴隷制度は、このような天性の美質を奪うものである事を証明した。その影響で、彼女の優しい心は石となり、仔羊のごとき性質は虎のごとき猛々しい性質に変わった。彼女は夫の教えを守り、夫と思想をともにし、やがては、夫よりも激しい気性となった。私が新聞を読んでいるほど、彼女を怒らせる事はなかった。怒りに形相を変えて飛びかかり、私から新聞をひったくった。部屋に一人でいようものなら、本を読んでいるのではないかと疑われ、呼び出されて弁明させられた。
それでも、私の勉強を妨げる事はできなかった。私は通りで白人の小さな少年と友達になった。そして、出会った少年をみんな先生にした。時間と場所を変えながら、彼らは親切に教えてくれた。その名前を挙げるのは控えよう。ただ、造船所近くのフィルポット通りの少年たちだと記しておこう。
私は少年たちと奴隷制度について話した。彼らは同情し、いつか良い事があると言ってくれた。彼らは大人になれば自由に振る舞える。私は12才で、一生奴隷のままだと思い詰めた。
この頃、奴隷制度について書かれた幾つかの本を読んだ。主人と奴隷との対話というのがあり、その結果、奴隷は解放された。宗教家のシェリダンは、奴隷制度を声高に非難していた。本を読むほど、私は奴隷商人を憎んだ。彼らはアフリカへ行き、私たちを盗み、奴隷の境遇に突き落とした。彼らは、もっとも邪悪な人間であり、もっとも卑劣な人間である。
読書を重ねるにつけて、オールド氏の予言通りになった。読書は、私の魂を苦しめ、苦痛を増すばかりだった。自分の惨めな境遇を教えてくれたが、そこから逃れる為の梯子を照らしてくれなかった。私は仲間の愚かさを羨んだ。自由への憧れが私を苦しめる余り、死を願う事さえあった。
自由になる希望がこれっぽっちさえなければ、私は自殺をしたか、犯罪でも犯していたに違いない。多くの人の話を聞くうち、奴隷廃止論というのがある事を知った。これは救いだった。しかし、世間一般では、奴隷が逃亡したり、主人を殺したり、納屋に火を付けたりするのが、廃止論の影響だった。
やっと手に入れた新聞で、ワシントンでの奴隷制廃止や、奴隷の州間取引撤廃要求などを知った。少しは、光が胸にさした。
波止場で、ふたりのアイルランド人が石を降ろしていた。頼まれなかったが、手伝った。問われて奴隷だと答えると、こんな立派な少年がと同情してくれた。ふたりは北に逃げろと勧めた。北に友人がいると。私は警戒して、興味のない振りをしながら聞いた。白人は奴隷を逃亡させながら、報酬めあてで主人に突き出す事をたまにする。しかし、北ヘ逃げろという忠告は、しっかり記憶に留めた。
私はまだ幼かったので、逃亡など思いもよらない。それまでに、書く事を覚えようと思った。造船所の木材には、その用途によって頭文字が記されている。まず、これを覚えた。私はチョークを使って、塀や鋪道で書き方を学んだ。私の小さい主人のトマスは、学校で読み書きを習い、多くの練習帳を使った。私はそれを拾った。私はその余白に文字を書いて時間を過ごした。
祖母の悲しみ
私の元の主人のアンソニー大尉が亡くなり、遺産は息子のアンドルーと娘のルクレチア夫人とで等分する事になった。私の身柄は、まだここの所有だった。財産として評価を受ける為に、農場へ戻るよう求められた。私はここで生まれ、5才でロイド農園へ行き、今は11才くらいだった。
老若男女が、馬や羊と一緒に並べられた。誰もが無遠慮な検査を受けて、財産として評価された。その屈辱より恐ろしいのは、その後に来る分割である。アンドルー氏は放蕩と残酷で有名だった。つい三日前も、私の弟を倒し、その頭を靴で踏み、鼻と耳から血を流させた上、お前も同じ目に合わせると宣言した。
私はルクレチア夫人の所有とされ、ただちにボルチモアへ帰らされた。一ヶ月の留守が半年にも感じられた。
間もなく、ルクレチア夫人、アンドルー氏も、立て続けに亡くなった。それでも、財産は赤の他人の手に渡り、ただのひとりの奴隷も自由にはならなかった。一連の経過で、何が悔しいかと言えば、祖母の扱いだった。
祖母は一生涯を老主人に仕えた。その幼年時代から晩年までを見た。また、数多くの奴隷を産み、育てた。アンドルー農場の財産は、すべて祖母から産まれたと言っても良い。それへの報恩として、現在の所有者は、森の中の小さな掘っ立て小屋を彼女に送った。多くの子供、孫、ひ孫を育てながら、ひとりぼっちで生きてゆくのだ。12人の子を産んだ女が、晩年を孤独に過ごし、その遺体は土に埋められる事もない。
ルクレチア夫人の亡き後、夫のトマス氏は再婚した。オールド氏との間に確執があり、私を引き取ると申し出た。私は、ここの家族に未練はなかった。オールド氏はブランデー、妻は奴隷制度の影響を受けて、ふたりとも性格が不幸に変わっていた。未練があったのは、ボルチモアの少年たちだった。
主人の宗教心
私は、トマス・オールド氏の農場へ移った。ここには、私のほか、姉のエライザ、叔母のプリシラ、ヘニーがいた。
ここはけちで、私は生まれて始めて空腹を味わった。奴隷に充分に食べさせないのは、白人の間でもいちばん卑劣な行為とされている。豊富な食料が戸棚や燻製室の中で腐りかけているのに、女主人はそれを知りながら、私たちを空腹にさせた。
奴隷所有者はみな悪徳に染まるのが常であるが、尊敬に値する、たったひとつの美点を持たないでもない。しかし、オールド船長には、それがひとつもなかった。残忍で、吝嗇で、卑怯で、臆病な人だった。彼が奴隷を得たのは、結婚によってである。もとは、湾内を行き来する小舟の操縦者だ。奴隷所有者の中でも、人の力でなった者は最低だ。彼は奴隷からも尊敬を勝ち得られないので、主人ではなく、船長と呼ばれた。
8月、オールド氏はメソジストの集会に参加して感化を受けた。この家は、宗教家たちの家となった。多くの牧師たちが夕食に招待され、この家に泊まった。私たちを飢えさせながら、4人の牧師が泊まった事もあった。宗教は、オールド氏にも若干の感化を与えた。
叔母のヘニーは、子供の頃、火の中に落ちて、大火傷を負い、動きが不自由だった。オールド氏は、このびっこの若い女を縛って、血が出るまで鞭打ち、その後、何時間も放置していた。一日中縛ったままで、朝昼夜と鞭打った事もある。ヘニーは、荷物運び以外は役に立たない事も事実だった。宗教の感化で、オールド氏はヘニーを放免にした。それはほとんど、行き倒れにして餓死させるようなものだった。
近くに、オールド氏の義父のハミルトン農場があった。ここは気前が良くて、よそ者にも食べ物を恵んでくれた。私は悪いと知りながら、オールド氏の馬を逃がして、ハミルトン農場まで追い込む事があった。私は何度も鞭を受けたが、それを繰り返した。とうとう主人は、私を一年間、コヴェイ氏の農場へ預ける事に決めた。コヴェイ氏は、若い奴隷をうまく鍛えるので有名だった。また、コヴェイ氏はその間、安い料金で自分の農園を耕す事ができた。多くの奴隷所有者は、奴隷を一年間、コヴェイ氏に預けるのは有益だと考えていた。彼は、奴隷飼育者としての名声を確立していた。
奴隷飼育者と逃亡の計画
私は、農場の仕事には不馴れだった。物心ついてからは、ボルチモアにいた。だから、失態もあった。
コヴェイ氏は私に、牛の放牧と薪取りの仕事を同時にさせた。牛に車を引かせて森に行き、そこで牛を放して、自分は薪を集めるのだ。私は、牛の扱いを知らなかった。森の中で、何かに驚いて、牛はいきなり走り出した。車は木にぶつかり、石に躍り、散々な目に合った。私は今にも木に脳天をぶつけないかとはらはらした。
帰って事情を説明すると、コヴェイ氏は、事故現場へ案内させた。彼はゴムの木の若枝を三本切ると、ナイフで形を整え、私に上着を脱ぐよう命じた。私がもたもたしていると、彼は虎のような激しさで飛びかかり、着物を剥ぎ、三本の鞭が潰れるまで打ちまくった。この時の傷は、今も残っている。
私はコヴェイ氏のところに一年間いたが、最初の半年は、鞭で打たれずに一週間を過ごす事はなかった。コヴェイ氏は食べ物は充分にくれたが、食べる時間は5分だけだった。
コヴェイ氏は自分で農園の仕事もできる、数少ない白人のひとりだった。だからこそ、彼をごまかす事は不可能だった。彼はいつも、不意に私たちに近付いた。
私たちは彼の事を、「蛇」と呼んだ。とうもろこし畑で仕事をしていると、彼はしゃがんで近付いて、畑の真ん中でいきなり立ち上がり、働けと叫んだ。農園の木、藪、窓、どこにでも彼は隠れていた。また、多くの用事を言いつけ、家に帰るふりをして、途中で引き返し、隠れて様子を伺うという事もした。
彼はぺてんの神を信じていた。全能の神さえ騙した。家での祈祷は、いつも讃美歌で始まる。彼はわざと調子外れな歌を、堂々と歌った。私は、彼を哀れみながら祈った。
コヴェイ氏は若い頃、やっとひとりの奴隷を買った。キャロラインという名の、二十歳の女だった。彼はよその農場から、既婚の男奴隷を一年借り、キャロラインと一緒に住まわせた。その結果、コヴェイ氏の財産は増えた。
私はどんな天候の時も働かされた。雨が降っても、雪が降っても、彼は奴隷を農園に駆り立てた。どんなに長い昼も彼には短すぎて、夜まで働かされた。三ヶ月の訓練で、私は飼育された。私の快活さは消え、知性は衰え、読書欲も消えた。彼は私を家畜に変えた。
日曜日には自由があった。そんな時には、魂の底から自由の炎がひらめいた。しかし、結局、今の境遇を惨めに思うだけだった。
近くに湾があった。ともづなを解かれた白い帆船は、私よりも恵まれて見えた。もしも、泳ぐ事ができたら、飛ぶ事ができたら、と思われた。我慢して死ぬよりも、逃げ出して殺された方が良い。
コヴェイ農場での始めの6ヶ月は、あとの6ヶ月よりも惨めだった。皆さんは、人間がどうして奴隷にされたかを見た。今度は、奴隷がどうして人間になったかを見る。
1833年、8月、もっとも暑い日。ビル、ウィリアム、エリーと、私の4人は、送風機を使って小麦のより分けの仕事をしていた。私はひたすら、小麦を運ぶ仕事だった。夕方3時、私は倒れた。処罰が怖くて立ったが、送風機のそばまで来て、また倒れた。
コヴェイ氏がやって来た。ビルが、私の具合が悪くなった事を説明した。私が休んでいると、コヴェイ氏は私のわき腹を蹴って、立てと命じた。私は立ったが、また倒れた。コヴェイ氏はまわりにあった板切れで、私の頭を殴った。血がどんどん流れた。コヴェイ氏は私を放置した。冷静になった私は、元の主人に苦情を言うか保護を願おうと思った。
私は歩いた。しかし、森の中でまた倒れた。血は止まらなかった。
5時間かけて、頭から足まで血まみれになり、元の主人のところへ帰った。私は慎ましく、保護をしてくれるよう頼んだ。しかし、主人の答えは、明日の朝には帰れ、というものだった。
私は夜も朝も食べず、コヴェイ氏の農場へ向かった。しかし、コヴェイ氏が牛革の鞭を持って迫って来たので、また逃げ出した。
私は森に隠れた。その夜、私はよその奴隷のサンデーと出会った。彼には自由な身の妻がいて、その家へ帰る途中だった。彼は家へ案内した。私は事情を説明し、忠告を仰いだ。サンデーは手なれた忠告者だった。私はコヴェイ氏のところへ帰るべきだと言われた。ただし、と、ひとつの木の根をくれた。その木の根を右ポケットに入れているだけで、どんな白人もあんたを鞭打つ事はできなくなる。私も数年来、同じ木の根を持ち歩いているが、それからは一度も殴られた事はない。私は迷信は嫌いだったが、彼を喜ばせる為に、その木の根を貰った。
日曜日の朝に農場に帰ると、コヴェイ氏は非常に優しく、豚追いの仕事を言いつけて教会へ行った。私は、木の根の効能を信じた。
月曜日の朝、コヴェイ氏は馬屋の世話を言いつけた。私は喜んで指図に従った。馬屋の二階から干し草を降ろしている時に、コブェイ氏が手に縄を持ってやって来た。そして、私が二階から降りようとしている時に、私の両足を掴んだ。私は飛び上がったので、床の上に倒れた。コヴェイ氏は、今日こそは私を好き勝手にしようという魂胆だった。この時、どこからそんな精神が湧いてきたのか知らないが、私は戦おうと決心した。
コヴェイ氏は私の足を押さえていた。私は倒れたまま、彼の喉を掴んだ。私の抵抗が思いがけなかったので、コヴェイ氏は震え出した。喉からは血が流れた。コヴェイ氏はヒューズを呼んだ。ヒューズは私の腕を縛ろうとしたので、私は立って、その腹を蹴飛ばした。ヒューズは逃げ腰となり、コヴェイ氏も挫けた。
コヴェイ氏は、入り口のところに転がっていた棒を掴んだ。そこを私は、相手の襟を掴んで押し倒した。コヴェイ氏はビルを呼んだ。ビルは自分の仕事をするだけで、鞭打ちの手伝いはできないと逃げた。
その後、二時間も争いを続けた。コヴェイ氏は、抵抗しなかったら、こんなに鞭で打たなかったのに、と憎まれ口を叩いた。だが、実際は、一回も鞭を使う事はなかったのだ。
それからの6ヶ月、彼は腹を立てても、指一本、私に触れなくなった。時には、もう二度とお前を押さえつけはしないと言った。私は答えた。「その時は、あなたの方がひどい目に合うでしょう」
これが転機となった。この勝利による満足感は、この先に待つのが死であっても、それを償って余りあるものだ。奴隷の墓場から、自由の天国への復活だった。
なぜ、コヴェイ氏が、保安官を呼ばなかったのか、銃でけりをつけなかったのは謎だ。だが、コヴェイ氏は、一流の監督として評判を取っていた。その名声は大事だった。たかが16才の少年にてこずったとあっては、体面に関わったのだ。
(以下略)

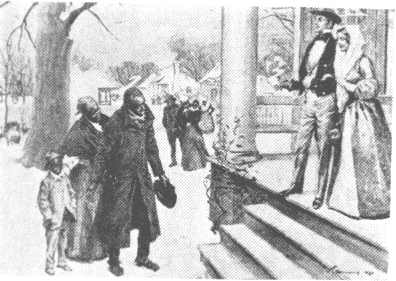
寸評
奴隷相手の、本当の鞭打ちは、怖いですね。(夜の歓楽街のとは違って)
人間が感情のままに振る舞えば、ここまで残酷になれるという事です。南部白人だけでなく、人間は、使用人や、立場の違う人に対しては、いつでもこうなりうるのです。
ほか、ウィキペディアでは以下の項目が注目です。
アメリカ合衆国の歴史 (1849-1865)
フレデリック・ダグラス(黒人)
ナット・ターナー(黒人)
ジョン・ブラウン(白人)
ハリエット・タブマン(黒人・女性)